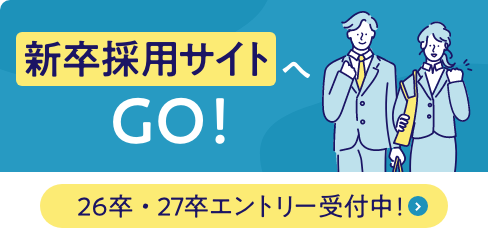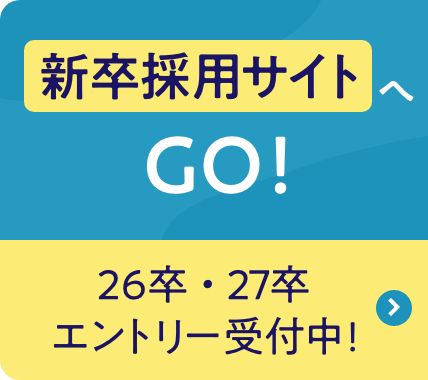水って何だろう? その3
「安心・安全の水道水」…それって「当たり前」なんでしょうか?
蛇口をひねれば、きれいな水が出ます。飲めるし、顔も洗えるし、料理にも使えます。
そう、言わずもがなではありますが、日本では「安心・安全な水道水」が当たり前。でも、「日本では」と書きました。視野を広げてみると、それが「世界の常識」ではないことに気づきます。
実際、SDGs(持続可能な開発目標)でも「安全な水とトイレを世界中に」という目標が掲げられているほど、清潔な水の確保は今もなお、国際的な課題なのです。
水は生きるために欠かせません。それを確実に得るために、人々は知恵をしぼり、道具を工夫し、手を動かしてきました。
では、私たちが水を「当たり前」に使えるようになるまでに、日本ではどんな歩みがあったのでしょうか。少しだけ、その歴史をひもといてみましょう。
井戸の歴史と文化は、思ったよりも奥が深かった(井戸だけに)
さかのぼること数千年前の日本では、川や湧き水を生活用水として活用していました。やがて弥生時代になると、稲作の広がりとともに「もっと安定して水を使いたい」という声が聞こえてくるようになったのでしょう。人々は井戸を掘り、水路をつくり始めました。
例えば福岡市の比恵(ひえ)遺跡群・那珂(なか)遺跡群では、弥生時代中期から古墳時代前期にかけてつくられた井戸が多数見つかっており、その数はなんと500基を超えます。
これらは素掘りのものが多く、直径はおよそ1〜1.5メートル、当時の深さは5メートルほどあったと考えられています。
井戸の中からは土器も出土しており、単に水をくみ上げるためだけでなく、水に関わる祈りや祭りとも関係していたことがうかがえます。

奈良時代の遺跡からは、井戸の構造にさまざまな工夫が見られるようになります。
奈良・平城宮跡では、杉の大木をくりぬいてつくられた手の込んだ井戸が出土しています。井戸の内壁が崩れるのを防ぎ、より安定して水を使えるように工夫されたものでした。
やがて時代は中世から近世へと進み、井戸は人々の暮らしにますます欠かせない存在となっていきます。
その中で、それぞれの地域が、それぞれの「水とのつきあい方」を育んでいきました。
例えば、岐阜県の高須輪中にあった「株井戸」という制度。これは江戸時代末期に生まれた仕組みで、新しく井戸を勝手に掘ることを禁じ、決められた井戸を地域で共有するというものでした。
今でいえば「共有資源の適正管理」といったところでしょうか。当時の人々はもっと実直に、「おたがいさま」の気持ちで成り立たせていたのかもしれません。
災害時の救世主!?井戸は今も健在です

今の暮らしの中で、井戸を見ることはほとんどなくなりました。それでも井戸は、確かに活躍しています。
そのひとつが、災害時における非常用の水源です。地域によっては、平常時から井戸と上水道を併用する取り組みも進められています。
上水道が当たり前となった今でも、井戸に関する技術や工夫は、災害への備えや、地域の水資源を守る工夫の中で、今も息づいています。
水の話は、もう少し続きます。次は「上水道」と「下水道」です。
平城京にもあった、なんと計画的な下水道
上水道は、家庭や施設に安全な飲み水を届けるためのもの。
下水道は、使ったあとの水や雨水を浄化し、自然へと還す役割を担います。
はじめに見ていくのは、下水道の歩みから。時を1300年前まで戻しましょう。
平城京では、街の衛生を保つために側溝がつくられ、雨水や汚れた水を効率よく流す構造が考案されていました。続く平安京でも、水を都市の外へと導くための水路が、都市設計の中に取り入れられています。
戦国時代以降も、下水の排水や処理には、その時代なりの工夫がこらされてきました。
仕組みの規模や方法は変わりながらも、「今の暮らしに合ったかたち」を探る姿勢だけは、ずっと変わらずに続いてきたようです。
上水道だけじゃない!?江戸の水供給ネットワーク
さて、ここからは「上水道」のお話です。
江戸時代に入ると、暮らしを支えるための水道整備が少しずつ本格化していきます。
なかでもよく知られているのが、江戸初期に完成した「玉川上水」。
多摩川の水を江戸の町に引き入れ、生活用水として供給したこの水路は、当時としては画期的なインフラでした。
地形の傾斜を利用して水を自然に流す「自然流下式」の仕組みで、一部には木製の水道管なども用いられました。この構造は、のちの近代水道の原型ともいえる技術です。こうした工夫の積み重ねが、江戸の町をより快適な都市へと変えていきました。
もっとも、江戸の町中すべてに水が行き届いていたわけではありません。
水道の整備が及ばなかった場所や、井戸水の質に不安があった地域では、「水売り」と呼ばれる人たちが水を運んでいました。
水売りたちは、神田川や玉川上水などから水をくみ、桶に入れて、てんびん棒や荷車で町をまわりながら販売していたのです。水道が引かれていない暮らしの中では、彼らのような水の届け手が欠かせない存在でした。
そして夏になると登場するのが「冷水売り」。冷たい水に砂糖や白玉を浮かべた、涼やかな飲み物は、暑い季節のちょっとした風物詩でもあったようです。

日本の近代水道、はじまりはだいたい160年前
明治時代、日本の水事情には大きな転機が訪れました。
西洋の技術が導入され、本格的な水道整備がはじまったのです。
その第一歩が、1887年(明治20年)の横浜。相模川の水を浄水場でろ過し、配水するという、日本初の近代水道が整備されました。
そしてこの技術は、函館、長崎、大阪、東京など、都市部を中心に広がっていきました。とはいえ、整備のスピードは決して速かったわけではありません。地方にまで水道が行き渡るには、まだまだ時間がかかります。
やがて時代は20世紀へ。家庭には洗濯機とお風呂が普及し、都市には工場やオフィスが増え、当然のことながら水の需要も右肩上がり。それに応えるかたちで、全国でダムが建設され、水資源の有効活用という視点からのインフラ整備も本格化していきます。
そして現在。と言いつつも少し前のデータで恐縮ですが、2021年度の時点で、日本の水道普及率は実に98.2%。ほとんどの家庭や施設に、清潔で安全な水が届けられています。
これは世界でもトップクラスの数字なんです。
流して終わりじゃない、これからの水とのつきあい方
上下水道は、これからの時代に向けて、少し難しい局面に差しかかっています。集中豪雨や渇水といった極端な気象。人口減少による施設の維持・管理の難しさ。そして老朽化が進むインフラ。いずれも、ちょっとやそっとで解決できるものではありませんが、見て見ぬふりをしていられる話でもありません。
そこで今、全国各地でさまざまな取り組みがはじまっています。下水処理の精度を高めた新しい施設や生活排水を適切に処理する合併処理浄化槽の導入。農村部では、その土地に合った排水施設が導入され、水環境を守る努力が続けられています。
家庭の中でも、変化が見えてきました。節水に気を配る人が増え、洗剤ひとつ選ぶにも「環境への優しさ」が基準になってきています。
これからの上下水道に必要なのは、持続可能性を意識した設計と運用。再生可能エネルギーを使った浄水施設や、排水を資源として生かす技術など、未来志向の試みが少しずつ形になりつつあるようです。
そして近年は、水そのものの価値を見つめ直そうという動きも広がっています。
名水百選を巡る旅、水と農の関係を伝えるカード、あるいはダムの機能を紹介するカードなどなど。気がつけば、水という存在が、文化や学びの入り口にもなっています。
名水百選、実は200か所あります
「百選」と名のつくものは、たいてい100で止まるものですが、こちらの「名水百選」は、どうも違いました。はじまりは1985年。環境庁(今の環境省)が、水質や景観にすぐれた湧水や河川、地下水などを100か所選びました。水の美しさを見つめ直し、地域の水環境を守っていくことが目的です。
それから20年ちょっとが経ち、2008年になると「平成の名水百選」という形で、さらに100か所が追加されました。
つまり、いまや全国に200か所の「名水百選」があるというわけです。
これらの名水の多くは、水源かん養保安林として守られています。また、地域の人々が中心になって、保全活動を地道に続けている場所も少なくありません。
名水百選の代表例
それでは以下に、日本各地の名水百選の中から、特徴的な4つの名水地をご紹介します。
羊蹄(ようてい)のふきだし湧水(ゆうすい)(北海道京極町)

北海道・京極町にある羊蹄のふきだし湧水は、ニセコ地方最大規模の名水スポット。湧水量は1日約8万トンと、日本でも屈指の水量を誇ります。羊蹄山に降った雨や雪が、火山性の地層でじっくりとろ過され、数十年かけて地表へ。標高250メートル付近の地層の境目から、冷たく清らかな水が勢いよく湧き出します。吹き出し口のすぐ横には取水口もあり、ボトル片手に訪れる人の姿が絶えません。
龍泉洞地底湖(りゅうせんどうちていこ)の水(岩手県岩泉町)

国の天然記念物にも指定されているこの洞窟では、神秘的な湧き水が主洞に沿って地下を流れ、いくつもの深い地底湖を形づくっています。現在は第三地底湖まで公開されており、その先に第四の地底湖があることも確認済みです。地元では古くから「ワックツ(湧口)」の名で親しまれてきましたが、1937年、文部省(現在の文部科学省)の調査により「龍泉洞」という名が与えられました。
瓜割(うりわり)の滝(福井県若狭町)

福井県・若狭町天徳寺の境内奥にひっそりと湧く瓜割の滝。その名は「瓜が割れるほど冷たい水」に由来し、1年を通して水温も水量も変わらないのが特徴です。古くは8世紀、泰澄(たいちょう)大師の時代から冷泉として知られ、五穀豊穣や病気平癒の霊験も信じられてきました。
白川水源(しらかわすいげん)(熊本県南阿蘇村)

熊本県を代表する水源池のひとつでは、年間を通じて水温14度、毎分60トンもの湧水があり、熊本市の白川の源流となっています。湧き水は自由に飲めて、持ち帰りもOK。加熱処理済みの水や空ボトルも販売されており、手軽に“名水の一杯”を楽しめます。
地域の農業と水の関係を凝縮「水の恵みカード」
「水の恵みカード」とは、地域ブランドの農産物と、それらの生育に不可欠な農業用水を農地に届ける水路やダムなどの農業水利施設(水の恵み施設)の役割が分かるトレーディングカードです。カードの表面には、地域ブランドの農産物の写真とその農産物の解説、カードの裏面には、農業用水路などの「水の恵み施設」とその役割などが記載されています。カードは、一般の方にも分かりやすく伝わるよう工夫されており、地元の農産物や農業水利施設についての理解を深めてもらうことを目的として作成されています。
このカードは、直売所や収穫祭、各地のイベント会場などで配布されており、水や農業への理解を深めるきっかけになるだけでなく、地域の魅力を見つめ直す機会としても注目されています。(※カードの配布時期・配布場所はカードによって異なります。)


▲山形県尾花沢市の村山北部土地改良区、尾花沢市役所(農林課)、大石田町役場(産業振興課)で配布される
「村山北部地区のお米・スイカ」(水の恵みカード提供元:農林水産省)


▲福岡県久留米市の(独)水資源機構筑後川下流用水管理所で配布される「筑後下流地区のあまおう」
(水の恵みカード提供元:独立行政法人水資源機構)
旅の目的になる名脇役「ダムカード」
「ダムカード」は、国土交通省や水資源機構が管理する全国のダムで配布されているコレクションカードです。
カードには、ダムの写真や所在地、型式、貯水量などの基本情報が載っていて、全国共通のフォーマットでデザインされています。
特徴的なのは、これらのカードが“現地を訪れることで手に入る”という点。言ってみれば、水のある風景を巡る小さな旅の“証明書”のようなものです。
実は、公式のカードだけでなく、各地の管理者が独自につくった“非公式カード”があったり、公式も期間限定版や記念カードがあったりして、つい集めたくなる魅力があります。

▲石手川ダムのダムカード(愛媛県松山市)
ダムカード配布場所:石手川ダム管理支所(愛媛県松山市宿野町乙69-3)
配布日時: 9:00~17:00(土・日曜・祝日を含む) お問い合わせ:089-977-0021

▲徳山ダムのダムカード(岐阜県揖斐郡揖斐川町)
ダムカード配布場所:徳山ダム管理所玄関受付
配布日時: 9:00~17:00(土・日曜・祝日を含む) お問い合わせ: 0585-52-2910
毎日ちょっと、水の味方になれること
日本は、昔から水に恵まれた土地です。
その水をどう使い、どう守るか。各地の暮らしの中で、井戸を掘ったり、ため池をつくったり、さまざまな工夫が積み重ねられてきました。そうした営みの先に、今の生活があります。
蛇口をひねれば清潔な水が出る。それが「当たり前」になった今だからこそ、水一滴の重みを、少しだけ意識してみませんか。
例えば、歯みがきの時に水を止める。シャワーの時間を少し短くする。洗剤を選ぶ時に排水への影響を意識する。
どれも小さなことですが、その一歩が、水や環境への優しさにつながっていきます。
「今日できることをひとつ」はじめてみることが、未来を少し変えるきっかけになります。
無理なく、気負わず、自分のリズムで。それがたぶん、一番長続きするやり方です。
◆福岡市博物館「井戸―遺跡編―」
https://museum.city.fukuoka.jp/archives/leaflet/395/index02.html?utm_source=chatgpt.com
◆奈良文化財研究所学報第40冊「平城宮発掘調査報告Ⅺ 本文 図版」
https://www.nabunken.go.jp/nabunkenblog/2020/12/BN0987631X.html?utm_source=chatgpt.com
◆遠藤 崇浩「株井戸の研究-輪中における革新的な地下水管理制度」
https://kaken.nii.ac.jp/ja/file/KAKENHI-PROJECT-26550101/26550101seika.pdf
◆JICA「日本の国土と水資源管理の歴史」
https://www.jica.go.jp/activities/issues/water/n_files/r03.pdf
◆東京都「玉川上水」
https://www.waterworks.metro.tokyo.lg.jp/kouhou/pamph/tamagawa?utm_source=chatgpt.com
![ミウラplus[ミウラプラス]](/assets/img/logo.svg)