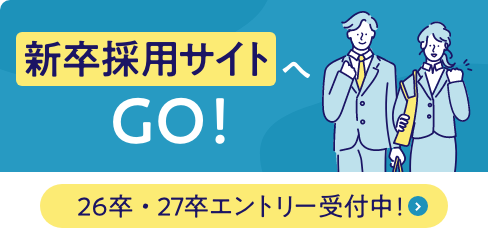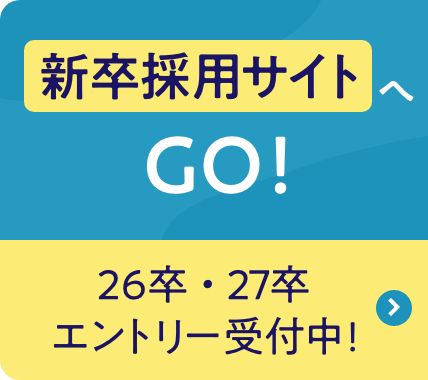フィールドエンジニア×設計者 本音トーク!座談会
お題は、『設計者の思い ×FEの思い』。
密接な繋がりがありながらも、なかなか直接意見交換をする機会がないFEと設計者。
第3回目は、いよいよFEと設計者がご対面。
お互いの気持ちを共有することで、どんな化学反応が起こるのでしょうか!?
島根・鳥取のスタッフが考える、次のミウラplusの企画は?! 【ミウラplus 出張編集部会議@山陰 part3】
①わかって欲しい!メンテナンスの苦労と努力
~フィールドエンジニアたちの本音編~
②設計者のキモチ
〜安全性・品質・コストetc…葛藤しながらやっています〜
③フィールドエンジニア×設計者 本音トーク!座談会
参加者プロフィール
もりた だいき森田大貴
MORITA Daiki
八王子中央メンテ 主任
2015年入社。趣味はゴルフ。料理好きで、お酒のアテを作って晩酌することも。得意料理はアヒージョ。今の悩みは、異動がないこと⁉

しらかた たかと白方誉人
SHIRAKATA Takato
広島北メンテ 主任
2009年、製造グループ会社の三浦マニファクチャリング入社。自らの希望で、2018年に三浦工業に移籍。趣味はスポーツ観戦。公的資格取得にチャレンジ中…!

よしおか りょうた吉岡凌汰
YOSHIOKA Ryota
三河中央メンテ 主任
2016年入社。三河西メンテ→三河中央メンテへ。趣味はゴルフ。ジビエが好き。海外勤務を志望しており、社内の「グローバル人材認定プログラム」を受講中。

かみや よしてる神谷 佳輝
KAMIYA Yoshiteru
ものづくり技術部 ものづくり技術課 係長
2006年入社。技術部量産設計課、アメリカ駐在部(5年間)を経て、ものづくり技術課へ。国内ボイラの量産維持対応を行っている。特技は数字を覚えること。

やまうち こうた山内 孝太
YAMAUCHI Kota
ボイラ技術部 ボイラ技術課 主任
2007年入社。流体センサ技術部、熱機器特需部、グローバル技術部、熊谷支店(6年間)を経て、ボイラ技術部へ。標準ボイラの量産維持・品質向上を行う。単身赴任のため、家族とのTV電話が楽しみ。

よしたけ じゅん吉武 淳
YOSHITAKE Jun
ボイラ電機技術部 ボイラ電機技術課 主任
2015年入社。電機技術部、グローバル技術部を経て、ボイラ電機技術部へ。国内ボイラの電機設計、海外ボイラの電機設計支援を行う。趣味はスポーツ鑑賞(特に相撲)。

省スペースにこだわる理由
編集部:早速ですが、設計者の方々に質問です。ボイラがコンパクトになっているがゆえに、「メンテナンス作業がスムーズに行えない」という声もあるのですが、省スペースにこだわる理由や重要さを教えてください。


そのような背景もあって、私がレイアウト設計を担当した「小型貫流蒸気ボイラSQ-3000AS」も、スペックを突き詰めて、幅1110mmとコンパクトに収めました。


でも、製品がリニューアルされると、限られた製品内部のスペースにどんどん新しい部品が追加されていく。お客様にとっては、故障しにくく、使い勝手の良いボイラにはなっているかもしれないけど、実際メンテナンス作業をするミウラのフィールドエンジニア(FE)からすると非常に作業がしづらくなってしまっているのが現実です。


例えば、昔は剥き出しで火傷のリスクも高かった「降水管」。今は断熱材を巻くことで、省エネスペック向上と火傷防止につながるよう改善した事例もありますね。

設計時にFEの意見って、反映してくれているのでしょうか?

現在(2024年11月時点)、62名の社員から書き込みをいただいておりますが、優先順位をつけてできるだけ製品に反映する方向で調整しています。


お客様に喜んでもらえて、かつFEの負担も減らせられる製品を作りたくて、我々も日々頭を悩ませながら設計しています。





設計者へのありがとうの声
編集部:FEの方々からお悩みの声はいろいろと聞かせていただきましたが、「改善されてよくなった」という声もぜひ聞かせてください。

ボイラのSQ-ASにO₂センサがついたのは、めちゃくちゃいい進化だったと思いますよ!これはお客様にとっても、我々FEにとっても大きな進化でしたね。
ボイラがO₂センサで検知した数値をもとに、最適な燃焼量なるようにリアルタイムで自動調整してくれるんですよね。
損失を低減できて省エネにつながりますし、我々FEにとっても作業時間を削減できるし、たくさんのメリットがあります!


ほかにも、遠隔で燃焼調整ができるようになったらいいのにな~。

編集部:ぜひ、他にもこういう喜ばしいネタを聞かせてください!(笑)

編集部:なるほど。こういう感謝の声って、なかなか届いてきませんか?



製品作った人リストつくったら、おもしろいかもしれませんね!




SZは鈴木さんが作ったっていう噂ありますよね?


あったらいいな!製品開発のミライ
編集部:製品に関して「こんなものがあったらいいな!」という声はありますか?





編集部:設計者の方々がここ数年で力を入れていることって何でしょうか?

今後、どの燃料にでも対応できるように水素以外にもアンモニアなど、新燃料のボイラの開発を進めています。

現在、ミウラでは「水素燃料ボイラ」も販売していますが、世間一般的には水素供給はこれからなので、副生水素が発生する業界でしか活用できないのが現状ですよね。

新製品開発の時は、他社が先に特許を取っていたら手を付けられないので、先手を打って取り組む必要があるんです。
編集部:世界中でカーボンニュートラルに向けた取り組みが進み、各企業もCO₂削減目標を掲げて必死に取り組んでいますもんね。これからのミウラの製品開発にも、乞うご期待!です。
設計者に聞く!素朴な疑問とモチベーション
編集部:FEから設計者に、ぜひ聞いてみたい話があるそうですが…。

設計者の方々って、メンテンナンス作業を一通り行ったことはありますか??あの…決して煽っているわけではなくて、素朴な疑問です。




編集部:現場の様子や状況を肌で感じたうえで、製品開発に取り組むことも重要そうですね!ほかにも聞いてみたいことはありますか?




在庫が残っている期間中に代替品を見つけてきて、複数の関連部署に声をかけて、無事に切り替えることができたらホッとしますよね。


編集部:ものづくりが止まらないように陰で支えながら、会社の方向性を汲み取って未来に向かって動く。それが設計者なんですね。
そして実際に手を動かし、お客様ともコミュニケーションを取りながら、会社の軸となる「メンテナンス」を支えてくれているのがFE。
ミウラにとっては両者とも、とても大切な役割を果たしてくれていますね。
今回のように、コミュニケーションを取り、お互いに力を合わせながら、よりパワーアップしたミウラを作っていきましょう!
まとめ
座談会のあとは、実習場へ。話題に出たお互いの主張を、実際の機械を見ながら説明し合いました。「確かにこれは大変ですね…」「なるほど、こういう意図でここに設置されているんだ」など、お互いに納得の声や笑いが出る、よい時間でした。
密接な繋がりがありながらも、なかなか直接交わる機会がないFEと設計者。今回、とても充実した意見交換ができたと思います。
今後も、ミウラの同志として、感謝の声を伝え合い、相互理解を深められるような交流ができる仕組みが整えばよいと感じました。

文中の「最適な空気量となるように」を「最適な燃料量となるように」に訂正いたしました。
(2025年3月4日)
![ミウラplus[ミウラプラス]](/assets/img/logo.svg)